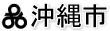二〇〇八年四月三〇日に沖縄市が「こどものまち」を宣言してから今年で一〇年を迎える。
今回は、戦後の混沌とした社会の中で、非行にはしるこどもや居場所のないこどもたちのために奮闘した島マスと、大流行した風疹による聴覚障がい児の教育に奔走した仲本とみ・中根和子の記録をひも解き、こどものまち宣言に通じる先人たちの軌跡を振り返る。
(※本文中、当時の状況を記録した資料に記されている表現をそのまま使用している箇所がありますこと、並びに、敬称を省略いたしておりますことを、あらかじめお断りいたします。)
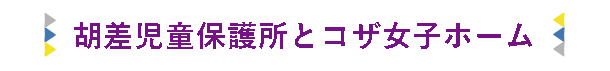
一、軍裁判立会厚生員として
一九四五年三月、沖縄本島への米軍の一斉艦砲射撃で開始した沖縄戦。激しい戦火をくぐり抜け、奇跡的に生きのびていたこどもたちは、終戦を迎えても、尚、厳しい環境に身をおいて生きていかねばならなかった。
一九五〇年頃から米軍の基地建設が本格化していく中、住民の間では、軍作業員が米軍の倉庫などから物資を無断で持ち出したり、基地内に侵入して物資を調達する、いわゆる「戦果」と呼ばれる行為が続出していた。これがこどもにも影響し、米軍基地周辺では〝戦果〟行為をするこどもも増えていった。
当時、基地内に侵入して捕まったこどもたちは、米軍の裁判にかけられ、すべて窃盗罪で刑務所に送られていたため、当時の群島政府が米軍と協議し、軍裁判に付されるこどもたちは、成人と区別して特別に保護することとなった。
群島政府は、コザ軍事裁判と那覇軍事裁判に「軍裁判立会厚生員」を配置し、こどもたちのための特別弁護人の役割を担わせた。コザ軍事裁判には、越来村駐在の厚生員を担っていた島マスが軍裁判立会厚生員として裁判に立会うこととなった。
立会厚生員となってからは慌ただしく、捕まったこどもと警察で面接して、いきなり裁判ということもあった。また、わずか十日間で十数人の裁判に立ち会ったこともあったという。
軍裁判で釈放されたこどもについても、問題は山積していた。帰る家のないこどもたちを引き取ってくれる施設はなく、島マスは自分の家で面倒を見ることにした。一時的な保護のつもりで自宅に引き取ったのだが、中には半年も行くあてのないこどももいた。
二、胡差児童保護所の開所
このようなやり方では限度がある。一九五二年、島マスは、家族の支えや多くの人びとの援助と協力によって、「胡差児童保護所」を開所した。
それからの島マスは、毎日、軍裁判に追い回される中、昼夜を問わず施設のこどもたちにもかかりきりとなっていた。
一時保護所はできたものの、こどもたちの食糧や衣類の確保、生活や学習面の指導など、施設を運営するには様々な困難があった。長期にわたって滞在する戦争孤児や肉親に引き取りを拒まれるこどももいた。
胡差児童保護所は、児童福祉法も整備されていない混沌とした社会状況の中、一九五四年に中央児童相談所が設置され、その一時保護所として引き継がれるまで、民間人の独自の力によってつくられ、運営されてきた施設であることを特筆しておきたい。
三、コザ女子ホームの開所
胡差児童保護所にはある悩みがあった。男子は、収容所孤児院などを前身とする「沖縄厚生園」や、児童の更生指導を目的として設立された「沖縄職業学校(後の沖縄実務学園)」に送ることができたが、当時は女子を受け入れる救護施設がなかった。
胡差児童保護所は、事実上、女子救護院の役割をも担うようになっており、一時保護所とは分離したかたちで女子救護院をつくる必要にせまられていた。
島マスは、たまたま譲り受けることとなったコンセット一棟を利用して女子児童の救護施設をつくることにしたが、多額の改修費を調達しなければならず、親戚などからお金を借り集め、大勢の人びとの寄付金や物資の提供などの協力を得て、一九五三年、「コザ女子ホーム」を開所した。
(※コンセット:米軍の組み立て式かまぼこ型兵舎で、払い下げられ学校等に利用された。)
島マスは、一九五二年に設立した琉球政府の社会福祉司としての勤務を担いながら、胡差児童保護所の運営に、女子ホームの指導に、と奮闘した。
女子ホームで保護したこどもたちの多くは、親や親戚の者がありながら家庭環境がきわめて複雑で、窃盗あるいは売春といった道を歩んで、警察や児童相談所から送られてきた。
島マスは、こどもたちを社会から隔離するのではなく、なるべく早く家庭に帰ることができるように、人への信頼を取り戻すことが大切であると考えていたため、女子ホームには門扉も塀もなく、監視などもせず、お互いの信頼関係を育むようにしていた。
しかし、中には女子ホームを逃げ出すこどももいて、連れ戻しに奔走し、保護するのに必死であった。小禄まで少女を探しに出かけ夜中になっても見つけることができず、那覇市役所の宿直室で一夜の宿をとったこともあった。また、大金を持ち逃げされたこともあった。この少女は映画館で同じ映画を何回もボーッとみていて、入場料だけ使われたお金がハンカチに包まれていた。「帰ろうね」と声をかけると素直についてきたという。
コザ女子ホームは、一九五四年に琉球政府の施設として移管し沖縄実務学園女子部となり、一九五六年には中央児童相談所の一時保護所として合併し、「コザ少女の家」と名称を変更した。私的な施設から公的な施設になっても、こどもたちと向き合う姿勢が変わることはなかった。

沖縄の日本復帰を目前に控えた一九七二年四月、中の町小学校に聴覚障がい児を対象とする学級が設けられ、中部圏域の八〇名余のこどもたちが入学した。
この学級は、一九六四年から一九六五年にかけて、沖縄全域に風疹(三日はしか)が大流行し、風疹に罹患した妊婦から出生した聴覚などへの障がいのあるこどもたちの学び舎として新設された。
小学校入学前の聴覚障がい児の幼児教育は、中部連合区教育委員会管区内の普天間・川崎・美里・中の町幼稚園の園舎を借用し、分散してなされていたが、こどもたちが小学一年生に進学するにあたって、中の町小学校に校舎を新築して統合した。
当時、四園を巡回してこどもたちの教育に奔走していた仲本とみと中根和子も、中の町小学校に赴任し、聴覚障がい児の教育を引き続き担うこととなった。
一、巡回教師として
遡ること一九六九年、琉球政府は、風疹による聴覚障がい児の聴能訓練を担当する指導者の養成が急務であるとして、日本政府に講師の派遣を要請した。
要請を受け、第一次教育指導団が来島し、各連合区教育委員会から選定された一二名の教師と母子二〇組を対象に、指導者講習会が開催された。中部連合区教育委員会からは、仲本とみと中根和子が参加した。
中部連合区教育委員会は、指導者講習会を受講し終えた両教諭を「巡回教師」として任命し、管区内を巡回する母子教育を開始した。聴能訓練等を主体とするものであったが、母親は常にこどもと共に学習し、教師と同じように指導技術を身につける、母親のための教育でもあった。
こどもたちには補聴器が無料配布されたが、巡回教師も補聴器を見るのは初めてであった。耳ざわりの悪い初めて見る物体に泣き出す子もいたが、何やら音を感じたらしいこどもがニコッと微笑む姿に思わず涙する場面も幾度かあった。
その頃、対象となるこどもたちは三歳児となっていた。巡回教師の二人は、まず教育相談を始めることにした。こどもたちを市町村単位で六グループに編成し教育相談をすることにしたのだが、巡回教師の苦悩は、筆舌に尽くし難いものであったという。
当時、障がいに苦しんでいるこどもたちの状況に対して社会の理解はほとんどなく、教室の確保でさえ大変な苦労であり、借用を認めてもらえないことも多かった。
借用を認められたものの、当日に出向いて行くと別の行事が優先され、遠くから来た母子たちを泣く泣く帰すこともあった。その無念たるや「どうしてよいか解らず、くやしさのあまり真昼間の大通りを、二人して涙を流して歩いた事もあった」という。
それでも、今日は勝連村、明日は具志川市、その次の日は宜野湾市へと、教育の場の確保や出席率を高めるための家庭訪問などで文字通り東奔西走の連日であった。
二、コザ社会保険事務所の仮教室
一九七〇年一月までには、ほとんどの連合区では教室が確保されていた一方、中部連合区は、コザ社会保険事務所の三階ホールを借用し、薄いベニヤ板と戸棚で四つに間仕切りした粗末な仮教室であった。そこは音響が筒抜けとなるため、訓練の場としては粗悪な環境で、オルガンやスピーカー、黒板などの教具が四畳から八畳程度の仮教室をより一層狭くした。
教育の場が固定化されたことによって、巡回指導は廃止となった。教師は増員されたものの、八学級に対して仮教室は四つしかなく、曜日ごとにクラスを分けて一日おきに母子を出席させるという不十分な状況であった。
少しでも多く教育日数を確保しようという現場の教師の熱意によって、中部連合区ホールを午前中借り受け、何とか週六日制を確保することができた。
三、公立幼稚園に入園
一九七一年、こどもたちも五歳児となり、公立幼稚園へ入園する年齢になった。
教師も増員され、普天間・川崎・美里・中の町幼稚園に、十一の特別学級を設け、風疹による聴覚障がい児の教育が正規の学校教育としてスタートした。
仲本とみと中根和子は、中部連合区教育委員会に属したまま、再び四園を巡回して指導助言することとなった。
公立幼稚園に聴覚障がい児の学級が位置づけられてからは、通常の学級の園児との統合教育(インテグレーション)も積極的に実施され、四園の統一研究会も数多く開催された。
レコードの音に全神経を傾けて精一杯リズムに合わせて歩こうと努力している子や、物語を話そうと体全体をふるわせて頑張っている子がいる。泣くことと笑うことしか表現できなかったこどもたちが、音を知り話せるようになっていた。研究会は教育の可能性と偉大さを実感する場であった。
風疹による聴覚障がい児教育は、一過性の単一学年であり前例がない。通常の学級担任よりも多くの研修活動と実践研究が必要であった。一過性の困難さゆえに、反省ややり直しのきかない厳しさがあった。
四、中の町小学校に入学
一九七二年、こどもたちも晴れて小学一年生となった。四園に分離していた聴覚障がい児の学級を中の町小学校に統合し、巡回指導にあたっていた仲本とみと中根和子も中の町小学校に赴任したのは、先に記したとおりである。
障がいのある児童は、様々な条件で個人差が大きいが、言語力やコミュニケーション能力が身についている子は、通常の学級へ入級し、その日課が終了すると、聴覚障がい児の学級に来て、学級特有の訓練や教科の補習を行った。
小学五年生になると、自学自習の態度もかなり身につき、言語力も豊富になっていた。そして、教科の補習も自力でやれるように指導を受け、出身市町村の小学校へ転校していった。
こどものまち宣言は、二〇〇八年四月三〇日、「こどものたちの主体的な活動を応援し、こどもたちが夢にむかって元気にたくましく育つ環境づくり」を基本理念に、議会の議決をもってなされた。これは、こどもを社会の成員としてその主体性を尊重するとともに、こどもを社会で擁護していくという、市民総意の決意の表明とも言える。
今回掲載した先人たちの軌跡と、今日、家庭や地域あるいは職場でこどもに寄り添うすべての市民との間には、時代を超えて相通ずる沖縄市の土壌がある。
このような土壌から誕生した「こどものまち宣言」は、市民全体で、常にこどもに光を当て、こどもの最善の利益を絶えず追求する姿勢を省みる〝標〟として存在し続ける。こどものまちづくりに「もうこれでよい」という終着点はない。
「島マスの頑張り人生」
「中部地区社会福祉の軌跡」
「コザ市史」
「沖縄市学校教育百年誌」
「沖縄の特殊教育史」
「沖縄の戦後教育史」